

COLUMN
投資初心者なので、新NISAのうちのつみたて投資枠を活用した投資から始めたいという人もいるのではないでしょうか?つみたて投資枠の対象商品は、投資リスクを抑えて運用ができる長期・分散・積立投資に適している商品が揃っているため、投資初心者におすすめの制度と言えます。
この記事では、つみたて投資枠のメリットとデメリットや投資初心者におすすめの理由、つみたて投資枠を始めるときにおさえておきたいポイントについて解説しています。
つみたて投資枠とは、2024年1月にスタートした、投資未経験者や初心者の長期・積立・分散投資をサポートするための非課税制度で、2023年までのNISAのつみたてNISAにあたる部分です。
つみたて投資枠は日本に住む18歳以上の人であれば、誰でも口座開設ができます。
一般的な投資では、売却益に対して20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金がかりますが、つみたて投資枠の口座で運用した場合は税金がかかりません。
またつみたて投資枠の対象商品は、国が定めた要件を満たした株式投資信託やETF(上場投資信託)に限られます。これらの商品に積立投資をして得られた売却益や、株式投資信託、ETFの分配金が非課税になります。
関連コラム:新NISAとは?旧NISAとの違いを徹底比較!【2024年最新】
つみたて投資枠は年間120万円までは、投資の売却益や株式投資信託、ETFの分配金に税金がかかりません。また非課税で運用できる期間は無期限になりました。ただし無制限に毎年120万円まで投資できるわけではありません。つみたて投資枠では、非課税で投資をできる限度額(生涯非課税限度額)が1,800万円となっています。
同じく非課税で運用できる制度に、成長投資枠がありますが、成長投資枠はまとまった資金を短期間で運用したい人向け、つみたて投資枠は少額で長期運用したい人向けの商品と言えます。
【つみたて投資枠と成長投資枠の違い】
|
つみたて投資枠 |
成長投資枠 |
|
| 対象年齢 | 18歳以上 | |
| 非課税期間 | 無期限 | |
| 年間最大非課税枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税枠総額 | 合計で1,800万円(ただし成長投資枠のみの場合は1,200万円まで) | |
| 投資方法 | 積立投資のみ | 制限なし |
| 投資対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 上場株式・投資信託等※1 |
※1整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は除外
つみたて投資枠と成長投資枠の主な違いは以下の3つです。なお2024年からの新NISAは、つみたて投資枠と成長投資枠の併用ができるようになりました。
つみたて投資枠は、年間最大120万円まで投資の売却益と分配金が非課税になります。成長投資枠は年間最大240万円まで、投資の売却益と分配金、配当金が非課税になります。
非課税期間はつみたて投資枠、成長投資枠いずれも無期限となりました。 つみたて投資枠の対象商品には株式が含まれないため、配当金はありません。
つみたて投資枠は定期的・かつ継続的に積み立てる投資方法しかできません。
一方、成長投資枠は、積立投資も一括投資もどちらも可能です。
つみたて投資枠は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。 一方、成長投資枠は一般的な株式投資信託や上場株式も対象商品に含まれています。
ただし整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は対象外です。 |

つみたて投資枠は短期投資をしたい人には向いていません。
また積立投資しかできないので、投資を活用して大きな金額を準備したい人は、NISA口座の成長投資枠や課税口座の活用も検討しましょう。
対象商品はすべて元本割れリスクがある、損益通算や繰越控除が利用できないといった注意点も確認してください。
つみたて投資枠は商品ラインナップも仕組みも、長期投資を前提とした制度となっています。長期投資は、運用で得た利益を再投資する複利運用の効果を高められるというメリットがあります。
しかし短期投資では積立額も少なく、複利運用効果も小さいため大きく資産を増やすのは難しいでしょう。そのため、つみたてNISAは短期投資には不向きの制度と言えます。
つみたて投資枠が非課税で運用できるのは、年間120万円まで、月額に換算すると約10万円です。
老後に向けて大きな金額を準備したい人や、月10万円以上投資をしたい人などは、つみたて投資枠と並行して特定口座や一般口座も利用する必要があります。
特定口座や一般口座での運用の場合、運用益に対して20.315%の税金がかかります。
つみたて投資枠の対象商品を、すでに一般口座や特定口座で運用しているため、つみたて投資枠に資産を移行したいと考える人もいるでしょう。
しかし課税口座で運用しているETFや投資信託がつみたて投資枠の対象商品に含まれていたとしても、NISA口座に移す(移管)することはできません。
つみたて投資枠は積立投資しかできません。仮に残高不足でつみたてNISAに投資ができない月があった場合でも、2ヶ月分まとめて投資するといったことはできません。
計画通りに資金の準備ができなくなる可能性があるため、投資額が引き去りになる日が近くなったら、口座残高を確認しておきましょう。
つみたて投資枠は、投資未経験者や初心者の投資をサポートするための制度ですが、元本が保証されているわけではありません。
つみたて投資枠の対象商品はすべて元本割れリスクがあるため、長期・積立・分散投資でリスクを抑えた運用を心がけてください。
損益通算とは複数の口座の損益を通算できる制度です。しかし、NISA口座で保有している金融商品は、他の特定口座や一般口座で保有している金融商品と損益通算ができません。
例えば特定口座Aで30万円の利益が出ていて、特定口座Bで20万円の損失が出ている場合、特定口座Aの利益と特定口座Bの損失を相殺して残った10万円に税金がかかります。
しかし特定口座Aで30万円の利益が出ていて、NISA口座Bで20万円の損失が出ている場合、損益通算ができません。特定口座Aの利益30万円に税金がかかります。
また特定口座や一般口座で運用していて、損益通算をしても引ききれなかった損失がある場合、翌年以降最大3年間損失の繰り越しができます(繰越控除)。しかしNISA口座はこの繰越控除も利用できません。
つみたて投資枠は以下のようなリスクがあります。一時的な元本割れも許容できないときは、他の投資方法を検討しましょう。また余剰資金がない人や、短期でお金を増やしたい人もつみたて投資枠はやめたほうがよいかもしれません。
金融商品を長期で運用していると、価格が上がったり下がったりして、一時的に購入した価格を下回ることがあるかもしれません。また、ショック的な下落で購入価格を下回ることもあります。
運用期間中に購入時の価格を下回ったとしても、決済をしなければ損失は確定しませんが、一時的な元本割れも許容できないときは、つみたて投資枠での運用は避けたほうが良いかもしれません。
普通預金や定期預金であれば、元本保証があるため安心です。ただし金利が低いため、大きく資産を増やすことは難しいでしょう。
つみたて投資枠は定期的にお金を積み立てて、運用していくための制度です。積み立てるときは、余剰資金を使うよう心がけてください。余剰資金とは当面使う予定がないお金のことです。
余剰資金は以下の式を使って計算します。
| 当面使う予定がないお金=手取り収入-日常の生活に必要なお金(家賃・保険料・水道光熱費など)-近いうちに使う予定があるお金(車の購入費・教育費など) |
つみたて投資枠は余剰資金で行わないと、毎月残高不足で投資ができなかったり、積み立ててもすぐに使ってしまったりしてなかなか積立額が増えない可能性があります。
余剰資金がないという人は、生活費の見直しもあわせて検討しましょう。生活費の見直しは、一度見直すと、それ以降は何もしなくても見直し効果が継続する固定費を優先すると効果的です。
固定費とは毎月、定額で支払う支出のことで、通信費、生命保険料、自動車保険料、新聞購読料などがあります。
つみたて投資枠は定期的に少しずつお金を積み立てて運用する商品です。
価格が安いときに一括で購入して、値上がりしたタイミングで一括売却をするといった投資方法はできません。
1年、2年で資産を倍にしたいなど、短期でお金を増やしたい人は株式投資やFXを検討しましょう。
つみたて投資枠は短期間の値動きで一喜一憂してはいけません。その他つみたて投資枠で効率的にお金を増やすには、長期投資を心がける、投資額を一定額に保つといったポイントをおさえて投資を継続する必要があります。
金融商品は価格が上がったり下がったりを繰り返します。ときには購入したときの価格を下回ってしまうこともあるでしょう。しかし、つみたて投資枠のような長期投資を前提とした制度で投資する際には、短期間の値動きに一喜一憂しないことが大切です。
長期投資は継続していくと、価格が上がったり下がったりする値動きの振れ幅が次第に小さくなっていくという特徴もあります。
長期投資は一度始めたら、粘り強く継続することが大切です。ただし完全に放置をするのは禁物です。運用している投資信託の投資先の動向なども確認して、下がっているときには、回復の見込みがあるかどうかも確認しておきましょう。
つみたて投資枠を利用した投資の複利効果は、長期投資をするほど大きくなります。
つみたて投資枠のメリットを最大限生かすために、できるだけ長く投資を継続することが大切です。
投資リスクを抑えるためには、ドルコスト平均法という買い付け方法が有効です。ドルコスト平均法とは毎月1万円、2万円など、定期的に一定額を買い付ける投資方法です。
投資信託のように値動きをする商品は、定期的に一定額を買い付けることで購入単価が平準化されるメリットがあります。
リスクを抑えて投資をするには、今の投資信託の価格にかかわらず、投資額を一定に保つよう心がけましょう。
つみたて投資枠は年間120万円までなら投資の利益に税金がかからず、最大1,800万円まで非課税で運用できます。非課税で運用できる期間の制限はなくなりました。
また取扱商品が金融庁の基準をクリアした長期の積立、分散投資に適した投資信託に限られていること、制度そのものが長期投資に合わせた仕様になっていることから、つみたて投資枠はリスクを抑えて運用したい投資初心者におすすめです。
ただしつみたて投資枠は、どの商品も元本割れリスクがあります。はじめて投資をするという人は、まず少額から始めてみても良いでしょう。
資産運用の基本から実践的なノウハウなどを幅広く解説するコラムです。初心者の方にもやさしく、資産形成をこれから始める方や、すでに投資信託を活用している方にも役立つ情報をお届けします。

なかなか預貯金ができず、周りの人はどれくらい預貯金をしているのか気になっている人もいるのではないでしょうか?この記事では、年代別、世帯別の平均預貯金額や中央値のデータを紹介しながら、預貯金額の傾向について解説していきます […]

2024年1月に新NISAがスタートしました。また、インフレの影響もあり「貯蓄から投資へ」の流れが加速しています。しかし、基礎的な金融知識もなく、投資を始めるのは危険です。 このコラムでは、投資初心者が投資をする前に押さ […]
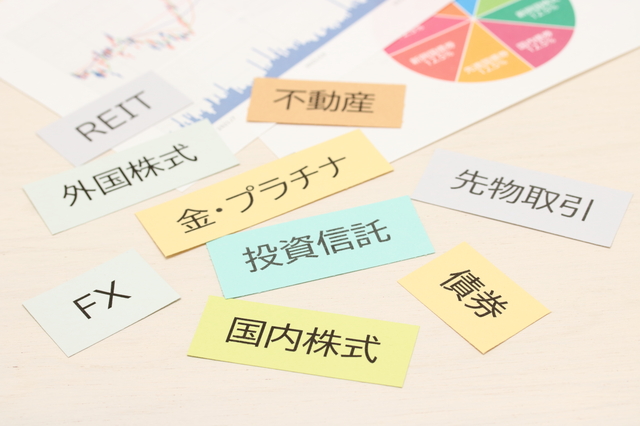
資産運用でお金を増やしたいけれど、何を選んで良いかわからないという方も多いのではないでしょうか?選んだ商品によっては元本割れリスクがあるため、金融商品選びは慎重に行う必要があります。 このコラムでは、これか […]
 アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説!2024年4月4日金融用語解説
アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説!2024年4月4日金融用語解説 米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説2024年5月28日金融用語解説
米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説2024年5月28日金融用語解説 日本の借金は国民の借金?2023年1月18日経済・マーケット動向
日本の借金は国民の借金?2023年1月18日経済・マーケット動向 テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介2024年7月31日金融用語解説
テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介2024年7月31日金融用語解説 投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】2023年2月24日資産運用
投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】2023年2月24日資産運用