

COLUMN

20代で貯金をしているものの、どれくらい貯金をすれば良いのか分からず不安が消えないという方もいるでしょう。20代は結婚や出産、住宅購入など、大きなライフイベントを経験する可能性が高いため、早めに貯金をして準備しておくことが大切です。
この記事では20代の平均貯蓄額や、20代以降でかかる費用、貯金をするためのポイントについて解説しています。
周りにいる20代はどれくらい貯蓄をしているのでしょうか?公的データをもとにした、20代の平均貯蓄額や貯金割合を紹介します。
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」の調査によると、20代の平均貯蓄額は、預貯金や保険、株式、債券、投資信託といった金融資産を保有していない世帯を含む場合、単身世帯が121万円、二人以上世帯が249万円です。一方、金融資産保有世帯の場合、単身世帯が219万円、二人以上世帯が403万円となっています。
この結果を見て、思ったより多いと感じた方もいるのではないでしょうか。平均値はデータの合計をデータの個数で割って算出します。20代の方のなかにも、1,000万円、2,000万円という貯蓄を持っている世帯があるため、平均値はどうしてもそちらに引っ張られてしまいます。
そのため、統計を見る上では、中央値もあわせて確認することが大切です。
中央値とはデータを並べたときに、中央に位置する値のため、一部の極端な値の影響を受けにくい点が特徴です。
20代の貯蓄額の中央値は、金融資産を保有していない世帯の場合、単身世帯が9万円、二人以上世帯が30万円、金融資産保有世帯の場合、単身世帯が103万円、二人以上世帯が171万円となっています。
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」の調査より、貯蓄をしている人の割合は単身世帯で56.1%、二人以上世帯で63.2% となっています。
さらに金融資産保有額と割合も見ていきましょう。
20代はまだ収入が低く、収入を得られるようになって時間が経っていないことから、十分な貯蓄ができておらず、金融資産非保有を除けば100万円未満の割合が多くなっています。
一方、わずかですが2,000万円、3,000万円など、大きな金額を貯蓄している世帯もあります。
| 金融資産保有額 | 金融資産を保有していない世帯 | 金融資産保有資産世帯 | ||
| 単身 | 二人以上世帯 | 単身 | 二人以上世帯 | |
| 金融資産非保有 | 43.9% | 36.8% | – | – |
| 100万円未満 | 23.0% | 21.6% | 40.9% | 34.3% |
| 100~200万円未満 | 10.9% | 9.9% | 19.5% | 15.7% |
| 200~300万円未満 | 5.3% | 8.2% | 9.4% | 13.0% |
| 300~400万円未満 | 4.9% | 4.7% | 8.8% | 7.4% |
| 400~500万円未満 | 2.6% | 4.7% | 4.5% | 7.4% |
| 500~700万円未満 | 4.0% | 4.1% | 7.1% | 6.5% |
| 700~1,000万円未満 | 2.2% | 2.3% | 3.9% | 3.7% |
| 1,000~1,500万円未満 | 1.6% | 1.2% | 2.9% | 1.9% |
| 1,500~2,000万円未満 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2,000~3,000万円未満 | 0.0% | 2.3% | 0.0% | 3.7% |
| 3,000万円以上 | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.9% |
| 無回答 | 1.6% | 3.5% | 2.9% | 5.6% |
国税庁長官官房企画課「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、年間平均給与は20~24歳が273万円、25~29歳が389万円となっています。 全体平均が458万円のた め、20代は全体平均よりも平均給与が下回っていることが分かります。
また金融広報委員会「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」より、20代の年間手取り収入からの貯蓄割合は単身世帯が平均18%、二人以上世帯の平均が14%です。
手取りは給与収入の75~85% と言われているため、20代の貯金額はおおよそ以下の通りと考えられます。
| 年齢 | 平均年収 | 手取り額(平均年収×75~85%) | 年間貯金額(単身世帯) | 年間貯金額(二人以上世帯) |
|
20~24歳
|
273万円 |
約204~約232万円 |
約36~約41万円 |
約28~約32万円 |
|
25~29歳
|
389万円 |
約291~約330万円 |
約52~約59万円 |
約40~約46万円 |
世帯によって状況は異なるため一概には言えませんが、貯金額の目標を立てたい方は上記の金額を参考にすると良いでしょう。

普段の収入で、生活費がまかなえればそれでよいというわけではありません。なぜなら人は一生の間に、大きな「ライフイベント」を経験するからです。どのようなライフイベントを経験するかは人それぞれですが、ここでは20代以降で考えられる代表的なライフイベントと、かかる費用の目安を紹介します。
将来、結婚を希望している方は、結婚費用を準備しておく必要があります。
リクルートブライダル総研「ゼクシィケッコントレンド調査2023」によると、挙式・披露宴・ウェディングパーティにかかる費用の総額は平均327.1万円 です。
ただしご祝儀の他、ご両親から援助を受けられる可能性もあるため、必ずしもすべて自己負担になるわけではありません。
ご祝儀総額の平均は197.8万円 、また親から援助があったと回答した方は73.5%で、援助のうち、挙式・披露宴・ウェディングパーティに使った金額の平均は163.7万円 となっています。
出産をする際にもお金がかかります。
出産にかかる費用は医療施設によって異なりますが、厚生労働省「出産費用の見える化等について」によると正常分娩で約48万円、異常分娩を含む場合は約46万円です。
さらに水道光熱費や、消耗品、医療機器の高騰などの影響で、出産にかかる費用は上昇傾向にあります。
| 異常分娩を含む | 正常分娩のみ | |
| 全施設 | 468,756円 | 482,294円 |
| 公的病院 | 420,482円 | 463,450円 |
| 私的病院 | 490,203円 | 506,264円 |
| 診療所 | 482,374円 | 478,509円 |
公的病院・・・国公立病院、国公立大学病院、国立病院機構等
私的病院・・・私立大学病院、医療法人病院、個人病院
診療所・・・官公立診療所、医療法人診療所、個人診療所、助産所等
ただし要件を満たし、手続きを行うことによって、公的医療保険から50万円の出産一時金を受け取ることができるため、 費用の一部をまかなうことができます。
しかしマタニティグッズやベビー用品など、出産に伴って発生する費用がある点は考慮しておく必要があります。
マイホームの購入を希望する場合は、住宅購入費用の準備が必要です。
住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」によると、住宅購入に必要な資金の平均はマンションで5,245万円、土地付注文住宅で4,903万円と年々上昇しています。費用を抑えたい方は、中古物件を検討してみましょう。
また立地や築年数で物件価格に違いが生じるため、購入を検討する際は、自身が住みたい地域の情報を把握しておくことが大切です。
【融資区分ごとの平均所要資金】
| 融資区分 | 平均所要資金 |
| マンション | 5,245万円 |
| 土地付注文住宅 | 4,903万円 |
| 注文住宅 | 3,863万円 |
| 建売住宅 | 3,603万円 |
| 中古マンション | 3,037万円 |
| 中古戸建 | 2,536万円 |
今後、災害や病気、けがなどで働けなくなる可能性もあります。万が一に備えて、予備費用も備えておきましょう。
緊急予備費用として用意しておきたい金額の目安は、生活費の3ヶ月~1年分です。仮に1ヶ月の生活費が18万円であれば、約54~約216万円となります。
20代のうちに貯金を始めておけば、大きなライフイベントに備えられる可能性があります。
20代で貯金をしていくためのポイントについて解説します。
家計簿をつけると、毎月の収入を何に使って、最終的にいくらお金が残ったかがひと目でわかります。
家計簿を振り返って、無駄な支出や、より安く購入する方法を見つけることで支出が抑えられるため、貯金をしやすくなるでしょう。
貯金が思ったようにできていないと感じたら、固定費の見直しをしてみましょう。固定費とは毎月かかる支出のことを指します。
具体的には家賃、水道光熱費、通信費、保険料、サブスクリプション代などが挙げられます。
固定費の見直しは、多くの場合、手続きに手間がかかる傾向がありますが、一度見直しをすれば大きな金額を節約できる可能性があります。
収入が入ってくる口座で貯金をしていると、いつでも引き出しができるため、欲しいものを見つけたときについ使ってしまう可能性があります。
貯金専用口座はつい使おうと思う気持ちにブレーキをかける効果などがあるため、むやみに貯金を引き出す機会が減らせるでしょう。
また「貯金の仕組み化」も組み合わせると、効率的に貯金専用口座に貯金がたまっていきます。
貯金の仕組み化とは、勤務先での財形貯蓄や積立定期預金などを活用して、自動的に貯金専用口座に貯まるようにすることです。一度手続きをしておけば、後は何もしなくても毎月お金が貯まっていきます。
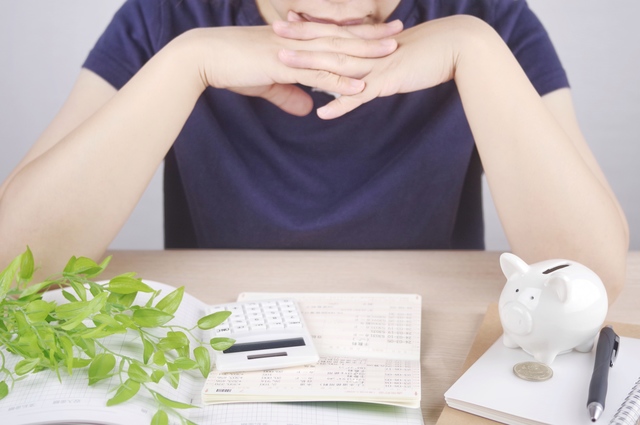
理想的な貯蓄額は手取りの20~30%程度と言われています が、自身で必要な貯金額を決めたい方は、必要になる金額と時期から逆算していきます。
例えば、結婚資金として5年後に200万円を用意したいと考えた場合、毎月約3万3,000円が必要になります。
ただ、将来控えているライフイベントは1つとは限りません。10年後に住宅購入も検討していて、10年後までに頭金300万円を用意したい場合、さらに2万5,000円が必要です。
つまり単純計算した場合、この方は毎月約6万円の貯金が必要ということになります。
さらに、並行して老後資金の準備も必要です。
このように最初からすべてのライフイベントに備えて貯金することは難しいかもしれません。だからといってやみくもに貯金をしても、目標や目的がないと長続きしない傾向があります。
必要な貯金額を算出するときは、まず自身の将来を思い浮かべ、希望するライフイベントに必要な金額と、必要な時期を書き出してみましょう。このライフイベントに必要な金額と時期を書き出した表を「ライフイベント表」といいます。
ライフイベント表を作成しておけば、5年間は2万5,000円を準備して、次の5年で住宅購入の頭金300万円を毎月5万円ずつ貯金する。住宅購入が終わったら教育資金や老後資金の準備に着手するといった計画が立てられるようになります。
計画を立てても、結婚をすればパートナーと意見の違いが生じたり、転職や転勤などで収入や勤務地が大きく変わってくるため、当初の計画が大幅に変わることはあるでしょう。
しかし日頃まったく貯金をしていなかった方が、急に収支を見直して貯金体質になっていくまでには時間がかかります。
ただしライフイベント表を作成して、目標を立て、貯金をしていたという行動は、例え予定が変わったとしても無駄にはなりません。
20代は大きなライフイベントが多く控えています。大きなお金は、時間をかけたほうが毎月の負担が少なくなるため、早めに準備をすることが大切です。例えば1年で100万円を貯金する場合は、毎月約8.3万円の貯金が必要ですが、5年であれば毎月約1.6万円とかなり少なくなります。
また無計画な貯金は挫折しやすいため、あらかじめライフイベント表を作成して、目標や目的を明確にしておきましょう。
<執筆者プロフィール>

金子賢司(かねこけんじ)
CFP
東証一部上場企業(現在は東証スタンダード)で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
 アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説! 2024.04.04
アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説! 2024.04.04  米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説 2024.05.28
米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説 2024.05.28  日本の借金は国民の借金? 2023.01.18
日本の借金は国民の借金? 2023.01.18  テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介 2024.07.31
テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介 2024.07.31  投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】 2023.02.24
投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】 2023.02.24  つみたて投資枠をやめたほうがいいケース3選|特徴やデメリットも解説2025.05.14
つみたて投資枠をやめたほうがいいケース3選|特徴やデメリットも解説2025.05.14 投資信託の利回り(リターン)とは?計算方法や選ぶときのポイントも解説2025.05.14
投資信託の利回り(リターン)とは?計算方法や選ぶときのポイントも解説2025.05.14 預貯金の平均はいくらぐらい?世代別の平均額や効率の良い方法も解説2025.04.18
預貯金の平均はいくらぐらい?世代別の平均額や効率の良い方法も解説2025.04.18 ロボアドバイザーとは?利用するメリット・デメリットや仕組みを解説2025.04.18
ロボアドバイザーとは?利用するメリット・デメリットや仕組みを解説2025.04.18 資産運用とは|年代別の始め方やおすすめの資産運用も解説2025.04.14
資産運用とは|年代別の始め方やおすすめの資産運用も解説2025.04.14