

COLUMN
なかなか預貯金ができず、周りの人はどれくらい預貯金をしているのか気になっている人もいるのではないでしょうか?この記事では、年代別、世帯別の平均預貯金額や中央値のデータを紹介しながら、預貯金額の傾向について解説していきます。
また、効率よく預貯金するコツについても解説します。預貯金をしたくてもなかなか続かない人、これから預貯金を始めようと思っている人はぜひ最後までお読みください。

収入や世帯構成、ライフスタイルの特徴が異なるため、預貯金の平均金額の傾向は年代によって異なります。
ここでは金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」をもとに、年代別の金融資産保有額を紹介します。
なお平均の預貯金額だけでは、極端に預貯金額が多い人の数値に引っ張られてしまうため、中央値も紹介しています。中央値とはデータを小さいものから並べたときに、ちょうど真ん中にくる値のことです。
この平均と中央値の違いを理解したうえで、各年代の預貯金額を確認してください。
20代単身世帯の預貯金額は平均が121万円、中央値は9万円、2人以上世帯の預貯金額は平均が249万円、中央値が30万円です。
自身で収入を得て働くようになってから間もないこともあり、単身世帯、2人以上世帯いずれも、各年代のなかで最も預貯金額が少ない傾向があります。
また単身世帯よりも2人世帯のほうが、世帯を持っている分、将来のライフイベントに備える意識が高く、預貯金額が多い傾向があります。
(単位:万円)
| 平均 | 中央値 | |
| 単身世帯 | 121 | 9 |
| 2人以上世帯 | 249 | 30 |
30代単身世帯の預貯金額は平均が594万円、中央値は100万円、2人以上世帯の預貯金額は平均が601万円、中央値が150万円です。
30代は、単身世帯と2人以上世帯の預貯金額の差が小さいという特徴があります。30代は世帯を持ち始める人が多く、教育費や住宅ローンの返済負担が増えるため、2人以上世帯の預貯金が難しくなっていると推測できます。
(単位:万円)
| 平均 | 中央値 | |
| 単身世帯 | 594 | 100 |
| 2人以上世帯 | 601 | 150 |
40代単身世帯の預貯金額は平均が559万円、中央値は47万円、2人以上世帯の預貯金額は平均が889万円、中央値が220万円です。
40代は30代に比べると単身世帯の預貯金額が減少し、2人以上世帯の預貯金額が増加しています。30代に比べると年収が増えるため、一般的に預貯金額は増加するはずです。
しかし40代は就職氷河期世代にあたり、安定した収入を得られていない層が存在する可能性があります。
(単位:万円)
| 平均 | 中央値 | |
| 単身世帯 | 559 | 47 |
| 2人以上世帯 | 889 | 220 |
50代単身世帯の預貯金額は平均が1,391万円、中央値は80万円、2人以上世帯の預貯金額は平均が1,147万円、中央値が300万円です。
50代に入るとさらに収入がアップするため、単身世帯、2人以上世帯ともに預貯金額が40代と比べて大幅に増加しています。子どもの教育費負担や住宅ローンの返済が終わる世帯が増え、預貯金をする余力が生まれることも理由として挙げられます。
また平均と中央値の乖離が大きく、預貯金ができている世帯とできていない世帯の差が拡大する傾向がある点も、50代の特徴と言えるでしょう。
(単位:万円)
| 平均 | 中央値 | |
| 単身世帯 | 1,391 | 80 |
| 2人以上世帯 | 1,147 | 300 |
60代単身世帯の預貯金額は平均が1,468万円、中央値は210万円、2人以上世帯の預貯金額は平均が2,026万円、中央値が700万円です。
60代は子育てにかかる費用や、住宅ローンの返済が終わる世帯がさらに増えるため、多くの世帯が老後に向けた資産形成を急ピッチで始める時期です。
特に2人世帯では、大幅に預貯金額が増加しています。
(単位:万円)
| 平均 | 中央値 | |
| 単身世帯 | 1,468 | 210 |
| 2人以上世帯 | 2,026 | 700 |
出典:家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和5年)|金融広報中央委員会「知るぽると」
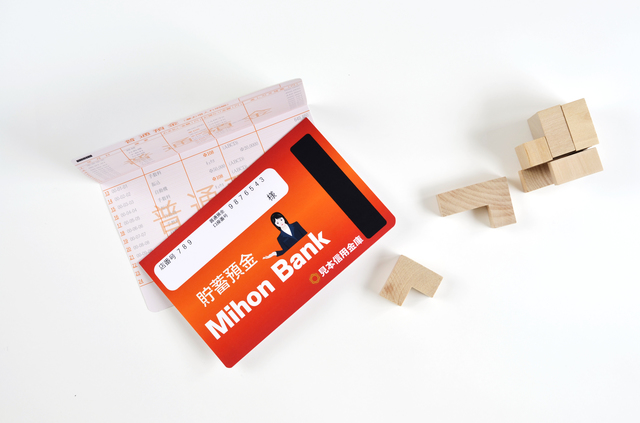
日本は預貯金が好きというイメージを持つ方もいるでしょう。しかしそのイメージは、あながち間違ってはいないようです。
2024年8月30日に日本銀行調査統計局が発表した「資金循環の日米欧比較」で、各国の家計の金融資産構成を比較したところ、日本は現金預金の割合が50.9%であるのに対し、アメリカは11.7%、ヨーロッパでは34.1%となっています。
また欧米は投資商品のなかでも、ハイリスク・ハイリターンにあたる株式投資の比率が高い点も注目すべき点と言えるでしょう。
【家計の金融資産構成】
(単位:%)
|
現金・預金 |
債務証券 | 投資信託 | 株式等 | 保険・年金・定型保証 |
その他計 |
|
| 日本 |
50.9 |
1.3 | 5.4 | 14.2 | 24.6 |
3.6 |
| 米国 |
11.7 |
4.6 | 12.8 | 40.5 | 27.7 |
2.7 |
| ユーロエリア |
34.1 |
3.1 | 10.6 | 21.5 | 28.7 |
2.0 |
欧米の金融資産構成で、株式や投資信託の比率が高いのは、教育環境によるところが大きいと考えられます。
日本でも2022年4月から、高校での金融教育が義務化されましたが、欧米ではすでに子どもの頃から金融教育が行われています。
日本ではまだ金融教育が十分行き届いていないことから、投資はリスクが高いものというイメージが先行し、積極的に学ぼうとする人が少ないのが現状です。
しかし高校での金融教育の義務化、新NISAのスタート、金融経済教育の機会を全国的に拡充していくことを目的としたJ-FLEC(金融経済教育推進機構)の設立など、国も金融リテラシー※向上に力を入れており、株式や投資信託への比率は高まっていく可能性が高いでしょう。
※経済的に自立し、より良い生活を送るために必要なお金に関する知識のこと
効率よく預貯金をするためには、預貯金の目的や目標を明確にすることが大切です。また預貯金ができない人は、家計簿をつけて家計の見直しをしてみましょう。計画的に預貯金をしたいときは先取り預貯金も有効です。
預貯金をするときは、預貯金の目的を明確にしましょう。預貯金は何のために、いつまでに、いくら預貯金をするのか明確にしないと、途中で挫折してしまいます。
目標が明確にならないときは「収入の20%」「生活費の6ヶ月分」など、数値を明確にした目安を設定すると良いでしょう。
預貯金をしたくても、毎月口座にお金が残らないという人は家計簿をつけて、自身の収支を洗い出してみましょう。家計簿をつけることで、毎月の収入を何にいくら使って、月末にいくら残ったかが一目で分かります。
仮に月末にお金が残らないのであれば、家計の見直しが必要です。夫婦の場合はお互いの支出について十分話し合い優先順位をつける必要があります。
家計の見直しは、一度見直すと、それ以降は何もしなくても効果が継続する、固定費を優先したほうが効率的です。
固定費とは、通信費や生命保険料、新聞購読料など、毎月定額で支払っている費用のことです。
一般的な預貯金は、毎月の手取収入から、生活費や趣味、雑費、食費などを使って、残った金額を貯めようとします。
しかし先取り預貯金は、手取り収入からまず目標とする預貯金額を引いて、残った金額で生活費などをやりくりする預貯金方法です。
積立定期預金などを活用して毎月先取り預貯金をする仕組みを作っておけば、さらに計画的に預貯金が貯まっていきます。
収入や世帯構成、ライフスタイルなどに特徴があるため、年代によって預貯金額の傾向は異なりますが、一般的には年齢を重ねるにつれ、収入が増えるため預貯金が増える世帯が多いようです。
老後は多くの世帯が、公的年金だけでは一般的な生活ができないと言われています。老後の備えをする前にも、結婚や教育費、住宅購入など大きなお金がかかるライフイベントが控えているため、計画的に預貯金をする習慣をつけておきましょう。
資産運用の基本から実践的なノウハウなどを幅広く解説するコラムです。初心者の方にもやさしく、資産形成をこれから始める方や、すでに投資信託を活用している方にも役立つ情報をお届けします。

目次 1 預貯金の平均金額はいくら? 1.1 20代の預貯金の平均金額 1.2 30代の預貯金の平均金額 1.3 40代の預貯金の平均金額 1.4 50代の預貯金の平均金額 1.5 60代の預貯金の平均金額 2 日本人は […]

2024年1月に新NISAがスタートしました。また、インフレの影響もあり「貯蓄から投資へ」の流れが加速しています。しかし、基礎的な金融知識もなく、投資を始めるのは危険です。 このコラムでは、投資初心者が投資をする前に押さ […]
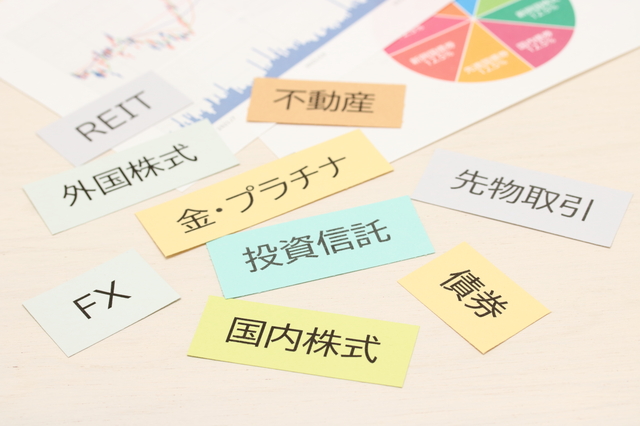
資産運用でお金を増やしたいけれど、何を選んで良いかわからないという方も多いのではないでしょうか?選んだ商品によっては元本割れリスクがあるため、金融商品選びは慎重に行う必要があります。 このコラムでは、これか […]
 アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説!2024年4月4日金融用語解説
アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説!2024年4月4日金融用語解説 米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説2024年5月28日金融用語解説
米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説2024年5月28日金融用語解説 日本の借金は国民の借金?2023年1月18日経済・マーケット動向
日本の借金は国民の借金?2023年1月18日経済・マーケット動向 テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介2024年7月31日金融用語解説
テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介2024年7月31日金融用語解説 投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】2023年2月24日資産運用
投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】2023年2月24日資産運用