

COLUMN
30代となり、将来のお金のことを考えると、「他の30代の方は一体どうやりくりしているのか」と気になる方もいるのではないでしょうか?この記事では、公的データに基づいた30代の平均貯蓄額や中央値を紹介しています。
またこれから待ち構える大きなライフイベントと、それにかかる費用の目安や、貯金の方法についても解説します。
30代で将来のお金について不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。
はじめに、30代の平均貯蓄額を紹介します。平均値だけでは偏った値になる可能性があるため、中央値についても見ていきましょう。
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」によると、30代(金融資産保有世帯)の平均貯蓄額は単身世帯443万円、二人以上世帯408万円、金融資産保有額の平均は単身世帯912万円、二人以上世帯856万円となっています。
【平均貯蓄額】
| 単身世帯 | 二人以上世帯 | |
| 20歳代 | 118万円 | 170万円 |
| 30歳代 | 443万円 | 408万円 |
| 40歳代 | 473万円 | 501万円 |
| 50歳代 | 839万円 | 663万円 |
| 60歳代 | 972万円 | 1,130万円 |
| 70歳代 | 929万円 | 964万円 |
【平均金融資産保有額】
| 単身世帯 | 二人以上世帯 | |
| 20歳代 | 219万円 | 403万円 |
| 30歳代 | 912万円 | 856万円 |
| 40歳代 | 964万円 | 1,236万円 |
| 50歳代 | 2,288万円 | 1,611万円 |
| 60歳代 | 2,240万円 | 2,588万円 |
| 70歳代 | 2,104万円 | 2,188万円 |
金融資産とは、預貯金の他、金銭信託、生命保険、損害保険、個人年金保険、債券、株式、投資信託、財形貯蓄などを指します。
また、こうした金融資産を全く保有していない世帯は、単身世帯で34.0%、二人世帯で28.4%にのぼります。
ただし平均値は、あくまでもデータをすべて足した後にデータ数で割った数値のため、一部、多額の貯蓄や金融資産を保有している数値に引っ張られてしまう可能性があります。
そのため、統計を見る上では、中央値もあわせて確認することが大切です。
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」は貯蓄額の中央値が存在しないため、金融資産保有額の中央値を見ると30代(金融資産保有世帯)は単身世帯300万円、二人以上世帯337万円となっています。
中央値とはデータを並べたときに、中央に位置する値のため、一部の極端な値の影響を受けにくい点が特徴です。そのため、より実感に近い数字になるといわれています。
【金融資産保有額の中央値】
| 単身世帯 | 二人以上世帯 | |
| 20歳代 | 103万円 | 171万円 |
| 30歳代 | 300万円 | 337万円 |
| 40歳代 | 500万円 | 500万円 |
| 50歳代 | 555万円 | 745万円 |
| 60歳代 | 1,100万円 | 1,200万円 |
| 70歳代 | 1,100万円 | 1,100万円 |
参考までに、30代の単身世帯と二人以上世帯の金融資産保有額と割合もご紹介します。
| 単身世帯 | 二人以上世帯 | |
| 100万円未満 | 22.0% | 17.2% |
| 100~200万円未満 | 9.3% | 13.8% |
| 200~300万円未満 | 11.2% | 10.6% |
| 300~400万円未満 | 9.3% | 7.8% |
| 400~500万円未満 | 6.1% | 6.3% |
| 500~700万円未満 | 8.4% | 9.3% |
| 700~1,000万円未満 | 5.1% | 7.3% |
| 1,000~1,500万円未満 | 11.2% | 8.8% |
| 1,500~2,000万円未満 | 2.8% | 3.0% |
| 2,000~3,000万円未満 | 4.7% | 3.7% |
| 3,000万円以上 | 6.1% | 5.6% |
| 無回答 | 3.7% | 6.7% |

30代は生活費だけでなく、将来訪れるライフイベントのお金も用意しておく必要があります。ライフイベントとは、結婚や子育て、住宅購入など人生の中でも大きなお金がかかる出来事のことです。
必ずしもすべてのライフイベントを経験するとは限りませんが、それぞれのライフイベントがどのくらいの費用となるのかを把握する際に役立ててください。
総務省統計局「家計調査(家計収支編)2023年」によると、30代の1ヶ月の平均支出は、二人以上世帯で27万5,491円、総世帯で241,932円です。
一般的に30代になると、結婚をして子どもを持つ世帯が増えてくるため、世帯の支出が増加し始める年代です。
【30歳の1ヶ月の平均支出】
| 総世帯 | 二人以上世帯 | |
| 合計 | 241,932円 | 275,491円 |
| 食料 | 64,792円 | 76,835円 |
| 住居費 | 27,342円 | 20,924円 |
| 光熱・水道 | 17,430円 | 21,064円 |
| 家具・家事用品 | 10,178円 | 13,655円 |
| 被覆及び履物 | 8,765円 | 11,127円 |
| 保健医療 | 9,408円 | 12,393円 |
| 交通・通信 | 37,365円 | 41,940円 |
| 教育 | 5,259円 | 7,997円 |
| 教養娯楽 | 28,344円 | 29,935円 |
| その他の消費支出 | 33,049円 | 39,621円 |
リクルート ブライダル総研が毎年発表している「ゼクシィ結婚トレンド調査2023」によると、挙式・披露宴・ウェディングパーティーの総額の平均は327.1万円です。
ただし結婚にかかる費用は地域性も大きく影響し、最も低い北海道では203.1万円、もっとも高い首都圏では356.3万円と差があります。
また、ご祝儀の平均は197.8万円、親からの援助の平均は163.7万円です。
ただし親からの援助を受けた人の割合は73.5%となっているため、さまざまな事情で援助を受けられない人も含んでいる点には注意が必要です。
厚生労働省 保険局保険課「出産費用の見える化等について」によると、出産費用の平均は正常分娩のみで482,294円、異常分娩を含めると468,756円となっています。
| 異常分娩を含む | 正常分娩のみ | |
| 全施設 | 468,756円 | 482,294円 |
| 公的病院 | 420,482円 | 463,450円 |
| 私的病院 | 490,203円 | 506,264円 |
| 診療所 | 482,374円 | 478,509円 |
公的病院・・・国公立病院、国公立大学病院、国立病院機構等
私的病院・・・私立大学病院、医療法人病院、個人病院
診療所・・・官公立診療所、医療法人診療所、個人診療所、助産所等
ただし、水道光熱費や消耗品、医療機器の高騰などの理由で、出産費用は上昇傾向にある点も考慮しておく必要があるでしょう。
公的医療保険の加入者には50万円の出産一時金が支払われますが、マタニティグッズやベビー用品など、出産に伴って生じる支出がある点も考慮しておきましょう。
住宅購入支援機構「フラット35利用者調査」によると、住宅購入した方の所要資金は、全融資区分平均で3,864.5万円となっています。
| 融資区分 | 平均所要資金 |
| マンション | 5,245万円 |
| 土地付注文住宅 | 4,903万円 |
| 注文住宅 | 3,863万円 |
| 建売住宅 | 3,603万円 |
| 中古マンション | 3,037万円 |
| 中古戸建 | 2,536万円 |
| 平均 | 3,864.5万円 |
物件価格は立地や築年数で大きく異なるため、自身が住みたい地域の情報を把握しておくことが大切です。
文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」によると、幼稚園(3年保育と仮定)~高校卒業まですべて公立の場合は約574万円、すべて私立の場合は約1,838万円がかかります。
また、大学でかかる費用は、文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」より、国立が約242万円、公立が約253万円、私立が約396万円となっています。
【小学校~高校までの教育費(年間)】
| 公立 | 私立 | |
| 幼稚園 | 16万5,126円 | 30万8,909円 |
| 小学校 | 35万2,566円 | 166万6,949円 |
| 中学校 | 53万8,799円 | 143万6,353円 |
| 高等学校(全日制) | 51万2,971円 | 105万4,444円 |
【大学入学~卒業までの教育費】
| 国立 | 公立 | 私立 | |
| 入学金 | 28万2,000円 | 39万1,305円 | 24万5,951円 |
| 授業料(年間) | 53万5,800円 | 53万6,363円 | 93万943円 |
子どもの教育費は大きなお金がかかるため、早めに準備にとりかかる必要があります。場合によっては奨学金の利用も検討しましょう。
文部科学省は、令和2年度より返済不要の給付型奨学金を拡充しています。
将来起こるライフイベントでは大きなお金がかかるため、計画的に準備をする必要があります。30代の方が貯金していくうえで、押さえておきたいポイントを解説します。
家計簿とは毎月の収入や支出を記録する帳簿のことです。市販の家計簿専用ノートを利用するほか、近年ではレシートを撮影するだけで支出が登録できる便利な家計簿アプリも登場しています。
家計簿をつけると、毎月の収入がいくらあり、何にどのくらい使ったか、いくら貯金ができたかが一目でわかります。
「余分な支出はなかったか?」「もっと節約できる支出はないか?」など、過去の家計簿を分析して改善することで、さらに貯金額が増やせるでしょう。
貯金の必要性を感じたら、あらためて現在の家計の見直しをしてみましょう。
家計の見直しは、毎月の支出のうち、定額またはほぼ定額で発生する「固定費」を優先的に見直すことをおすすめします。
代表的な固定費としては、家賃、水道光熱費、保険料、通信費などがあります。
固定費を優先的に見直したほうが良い理由は、手続きに手間がかかる傾向がある反面、見直すことができれば節約できる金額が大きいからです。
一方、食費や交際費など毎月、支出額が変動する「変動費」の見直しも効果がないわけではありません。しかし安い店を探し回る、商品ごとに安く買えるのはどこか比較するなど、労力の割に効果が少ない傾向があります。
計画的に貯金をしたい方は、給料などの収入が入っている口座とは別に、貯金専用の口座を開設しましょう。
貯金専用口座を作って貯金しておけば、欲しいものを見つけても衝動的に現金を引き出してしまう心配が減るためです。
また貯金専用口座を開設したうえで「先取り貯金」をすると、より計画的にお金を貯めやすくなります。
先取り貯金とは、積立預金や財形貯蓄などを使って、まず毎月の収入から貯金したい金額を貯金専用口座に移す仕組みを作り、残った金額だけでやりくりする方法です。

将来のライフイベントにかかるお金に備えるためには、効率的にお金を増やすことも大切です。ここでは3つの方法を紹介します。
毎月5,000円、1万円など定額を、毎月決まった日に積み立てることができる定期預金です。積立日や積立額がある程度自由に選べるため、自身の目的や必要な時期に合わせて、計画的に貯金ができます。
【メリット】
【デメリット】
iDeCoとは個人型確定拠出年金のことで、掛金を拠出し、自身で商品を選んで運用する制度です。掛金の全額が所得控除になるなど、税制面での優遇が受けられる反面、60歳まで引き出せないなどのデメリットもあります。
【メリット】
【デメリット】
NISAで資産運用をして効率的にお金を増やす方法もあります。NISAとは少額投資非課税制度のことで、NISA口座で運用すれば、運用益に税金がかかりません。
NISAは成長投資枠とつみたて投資枠の2つに分かれており、このうち成長投資枠は比較的リスクが高い商品も選ぶこともできるため、大きな利益が狙える可能性があります。
一方、つみたて投資枠は金融庁の基準を満たした投資信託からしか選ぶことができないため、成長投資枠に比べ選択肢は限定されています。
成長投資枠とつみたて投資枠は併用できるため、自身のリスク許容度や考え方などに応じて商品を選びましょう。
また1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)の非課税保有限度額や年間投資枠が決められており、この範囲内で自由に売買ができます。
投資信託などは元本割れ等のリスクがありますが、お金を増やしたい方は検討してみましょう。
【メリット】
【デメリット】
30代の平均貯蓄額は単身世帯が443万円、二人以上世帯が408万円となりました。
30代は生活費以外にも、大きなライフイベントが多く控えているため、計画的に貯金をして備えておくことが大切です。
家計の見直しや貯金専用口座を活用すれば、よりお金が貯まりやすくなるでしょう。
さらに効率的にお金を貯めたい方は、積立定期預金やiDeCo、NISAなどの活用もおすすめです。
資産運用の基本から実践的なノウハウなどを幅広く解説するコラムです。初心者の方にもやさしく、資産形成をこれから始める方や、すでに投資信託を活用している方にも役立つ情報をお届けします。

なかなか預貯金ができず、周りの人はどれくらい預貯金をしているのか気になっている人もいるのではないでしょうか?この記事では、年代別、世帯別の平均預貯金額や中央値のデータを紹介しながら、預貯金額の傾向について解説していきます […]

2024年1月に新NISAがスタートしました。また、インフレの影響もあり「貯蓄から投資へ」の流れが加速しています。しかし、基礎的な金融知識もなく、投資を始めるのは危険です。 このコラムでは、投資初心者が投資をする前に押さ […]
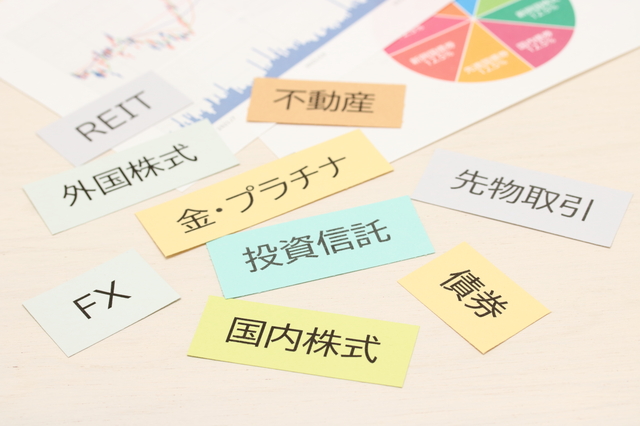
資産運用でお金を増やしたいけれど、何を選んで良いかわからないという方も多いのではないでしょうか?選んだ商品によっては元本割れリスクがあるため、金融商品選びは慎重に行う必要があります。 このコラムでは、これか […]
 アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説!2024年4月4日金融用語解説
アメリカ国債のデフォルト(債務不履行)とは?経済への影響をわかりやすく解説!2024年4月4日金融用語解説 米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説2024年5月28日金融用語解説
米国債とは?投資するメリットやデメリット、リスクなどをわかりやすく解説2024年5月28日金融用語解説 日本の借金は国民の借金?2023年1月18日経済・マーケット動向
日本の借金は国民の借金?2023年1月18日経済・マーケット動向 テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介2024年7月31日金融用語解説
テンバガーとは?2023年の達成銘柄を紹介2024年7月31日金融用語解説 投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】2023年2月24日資産運用
投資してはいけないファンドとは?【ブル・ベア型ファンド】2023年2月24日資産運用